
ここでは、不動産投資に限らず全ての投資に当てはまる重要なことと私が思っている事を列挙してみたいと思います。
(1)最初に支出を我慢する。
モノポリーや億万長者ゲームで遊んだことあるでしょうか? 私は小学生の頃、この「億万長者ゲーム」といったゲームが好きで、近所の友達としょっちゅう遊んでいた記憶があります。
このゲームは、単純に言うと「より早く」「より多く」投資した者が最後に最もお金持ちになり勝者になるといったものです。なぜなら、自分の買った不動産等のコーナーに他のプレーヤーがやってくるとお金を巻き上げることが出来るからです。このゲーム上においては現金を持っていても、その現金を使って快楽を享受できないため、どのプレーヤーも誘惑がないため、迷いも無くお金を貯めてひたすら投資し続け勝者を目指します。
しかしながら、いざ実際の生活においては、今の収入で出来る範囲内で最も良い生活をしてしまいます。これでは、投資するための資金など出来る訳ありません。
(借金して嗜好品を買うなど論外です・・)
(2)貯金を何に使うか
「貧乏父さん・金持ち父さん」(著:ロバート・キヨサキ)において、「財産とはキャシュフロー(利益)を生むものである。」といったような事が書いてありましたが、彼の言う通り、自分で使用する別荘は財産ではなく、利益を生む賃貸用不動産等が財産なのです。
(3)使うお金の種類
(1)でお金を貯めて(2)で利益を生む財産に投資をするのですが、これではいつまでたってもお金を使えずに幸せになれないじゃないかー!といった声が聞こえてきそうです。確かに永遠にお金を貯め続けて投資し続けるのもおかしいですよね。
「マルサの女」といった映画において、脱税経営者役の山崎努が マルサの女役の宮本信子に対し、「あんた、喉が渇いたらどうする? 喉が渇いた時はこうして喉の渇きを癒すんだよ。」(記憶で書いているので正しくは違うと思います)と言い、氷水が入った冷たいコップの外側に露結した雫を舐めてみせました。(要は元本を使うなんてとんでもないといったことですね。)
収入の増加に従い、もちろん生活費を上げていって良いのですが、収入が2廻りか3廻り上がった後に、テンポをずらして生活費を上げるだけで、再投資による資産拡大を達成し、生活水準も上げることが出来るのです。
投資を博打と考えてはいけません。知識と経験と努力に応じて長期的には必ず相応の結果になるからです。この相応の結果というのは二つの面があります。
知識と経験と努力に応じて良い投資が行えるのは当然ですね。今の時代、投資について極めて多くの情報に溢れています。受身の姿勢で入ってくる情報は、金融関係の会社の者が、その会社が儲かるための商品を販売にくる「広告宣伝」や「単なるセールスマン」から提供されるものと考えてください。本物の情報は、積極的に苦労しながら入手した情報の中で、自分が勉強と経験により身に付けた優れた能力で、頭を回転させてふるいをかけたものの中だけに、良い投資対象はあるのです。
それともう一つマーケットに不必要に揺さぶられないといった点が非常に大きいと思っています。
投資は当たり前ですが、キャピタルゲイン(安い時に買って、高い時に売って利益を出す)とインカムゲインを目的としています。しかしながら、大半の方が損をするのは、こうした事が分かっていても高い時に買って、安い時に売ってしまうからです。株式投資信託も人気がある時に買ったものは大きな損失を出して、誰も見向きもされない安い時期に買ったものほど大きな利益をだしています。知識や努力をしない人は、他人やメディアの言っている事を鵜呑みにし易く、実際のマーケットが暴落していると怖くなって、買うべきタイミングである時に逆に最安値近辺で売却してしまったり、マーケットが暴騰して儲かってくると気持ち良くなって追加で高いところで買い増しし続けてしまったりします。
努力して知識や経験を積めば、こうしたマーケットの誘惑に打ち勝つ事がより出来るようになります。
人間努力をすると、相応の見返りがとても欲しくなるそうです。考えてみればそれはそうだと思うのですが、これが投資家の意思決定を歪めます。不動産投資に限らず、何かに投資しようと思い勉強したとすると、強くもとを取るために買いたいといった衝動がおき、投資すべき時期でないにもかかわらず投資しまったりするのです。
内容が良く分からないものに投資してはいけません。理由は二つあります。
(1)騙される
私が社会人になりたてのころ、ある投資信託会社の運用において、運用するファンドの利回りが極めて良くなると売買を頻繁に行い母体である証券会社に売買手数料を落として利回りを下げておりました。当然、このファンドが市況に伴いマイナスの利回りが出てもその証券会社が補填などしてくれる訳もなく、そのまま損を投資家に負担させていました。
要は儲かった時は搾取され、損した時は全額責任をとらされる。更にファンドの利益が出ようが出まいが、固定の管理手数料までとられる始末・・。これでは損することが多いのは当たり前です。今はここまで酷い事は出来ないのでしょうが、多かれ少なかれこういった世界があることが多いため、投資対象はもとより、こういった仕組みを知らないものにたいしては基本的に投資すべきではありません。
(2)投資対象に自信が持てなくなる
投資は当たり前ですが、安い時に買って、高い時に売る若しくはホールドすることを目標とします。ただ、買う時が最安値である大底で買うことは奇跡でも起きない限り不可能です。ということは、買った後、ある程度下がり含み損を抱えることは当たり前のこととなります。この含み損を抱え、徐々にその含み損が拡大する局面で行われている投資に自信を持つことが出来なければ、大きな不安を抱くことになり非常に安い価格で売却してしまい大きな損失を被ることになります。
(3)ただし・・・
投資対象及び運用方法が分からないものを投資対象外にしてしまうと、極めて優れた投資対象であるにもかかわらず投資対象外にしなくてはなりません。よって、投資対象及び運用方法が分からない場合は、自分の投資予算において失っても全く気にならない程度の小額で「とりあえず試し・・」での運用を行ってみます。良く分からないで行った「とりあえず行った試し」での投資はマイナスになることの方が遥かに多いと思います。しかしながら、もしこの「とりあえず行った試し」でうまくいき徐々に投資金額を上げていった場合、投資金額を極めてゆっくりと上げてゆくことです。そうしないと、小額で何回にもわたって積み上げていった利益が、多額での投資1回で簡単に失い、またトータルで損失となってしまいます。ゆっくりと投資金額を上げてゆけば、トータルの利益がプラスのまま自信をより深めながら、その投資の持つパフォーマンスを享受出来るはずです。
更に厳しい事を言えば、こうして関門を突破して実際に利益を出してくれた投資対象及び運用方法であっても、本物かどうかは分かりません。投資対象及び運用方法に逆風が吹いている場合のパフォーマンスも確認した上でないと本物か否か判断はつかないのです。
「とりあえず行った試し」で行った投資の殆どは損をするとは思いますし、本物に辿り着くまで大変な手間と期間を要すると思いますが、本物の投資対象及び手法等に巡り合う事ができれば相当長期間に亘り、何回も利益を生み出し累計では相当の利益を与えてくれるはずです。
景気に波動があるように、投資物件の価格にも波動があります。この波動は、短期の波動、中期の波動、長期の波動と見方によりいくつもの波動があります。投資する価格を安く抑えるためには、基本的にこの波動において低い時点で投資を行う必要があります。相当の運用資金を保有しており、よって投資を何回もし続けられ技術や時間があれば、短期の波動で投資しても問題ありません。しかしながら、不動産のように多額の投資で何回も投資し続けることが困難なのであれば、相当長期なる期間でみた波動における安値時期に投資すべきとなります。勝てる確率が高い時だけ投資するといったことは、とても大切なことなのです。
投資価格の如何を問わず、投資したこと自体について是非が議論されたりすることがあります。しかし、これは基本的に間違いです。どんな投資でも全ては費用対効果でその是非が計られなければなりません。
仮に毎月10万円の利益を安定的に生み出す投資物件があり、これに投資したことが適切であったか否か考えてみましょう。この物件は年間120万円の利益を生み出しますが、この物件を120万円(利回り100%)で買えればこの投資は成功でしょうし、1億2千万円で買ったら(利回り1%)失敗です。これは極端な話ですが、有利な価格で売買できれば投資した時点で成功の相当部分が保証されるのです。逆に言えば、割高に投資を行った場合、それを取り戻すには、投資後の利益を更に増加させるといった極めて汗を流して大変な努力が必要になると言えます。
投資において効果は利回り・・。これに対し費用はリスクになります。では、リスクって何なのでしょうか? リスクとは利益の変動率(不確実性)のことなのです。利益が確実であればリスクでないのです。不動産への投資で利回りが(仮に)8%あるにもかかわらず、定期預金の利回り0.5%に預ける人がいるのは、不動産の方が儲かる可能性において高いとは思うものの、不動産価格が下がったり、トラブルが起こったりしてどういった結果になるか分からない(不確実性)からなのです。
ところで、「リスクとは不確実性である」 といいました。
仮に確実に墜落することが判明した飛行機に乗ることはリスクがあると考えるのでしょうか?
通常はそんな飛行機に乗るなんてリスクがめちゃめちゃある と考えられることでしょう。でも、ファイナンス理論におけるリスクは違うのです。確実に墜落する飛行機に乗ることはリスクがないと考えます。死にたくない方はそんな飛行機に絶対に乗らないでしょうし、墜落を経験したい方は希望通り確実に墜落を経験できるのです。
このように、不動産に投資する場合においては、将来最も起こりえそうな収益の予想を一つ(ベーシックシナリオ)だけ行うのでなく、最悪と最高の3つの可能性を自分で想像することによりリスクを把握し、このリスクと利回り(=収益÷不動産価格)を比較して割安か割高かを判断します。また、違う見方をすれば、その不動産のリスク(将来の予測収益の振れ幅)に見合う利回り(期待利回りといいます)を判断し、その不動産の収益をこの期待利回りで除すれば、投資対象の価値を計算することが出来るのです。
この利回りの計算について以下の点に注意して下さい。
投資は行わなくても損をしませんが、投資を実行した場合実際に損失が発生する可能性があります。
単に投資自体が怖いといった理由でなく、投資利回りが満足でないといった点で悩んだら投資しない事をお勧めします。
株式投資信託も人気がある時に買ったものは大きな損失を出して、誰も見向きもされない安い時期に買ったものほど大きな利益をだしています。実際に株式や不動産等に投資をしたことがある方だと実感してもらえると思うのですが、不動産を市況が低迷している時期に取得したものは、どの物件に投資しても大抵利益となっているでしょうし、不動産価格が高騰した頂点で取得したとしたら、どの物件に投資しても大きな損失を被ることでしょう。
要は、投資対象自体を今の相場に比べて割安か割高か判断することが出来る能力よりも、今が投資すべき時なのか、投資してはいけない時期なのか判断することの能力の方が遥かに重要なのです。
「投資対象の選別よりいつ投資したかが重要」と書きましたが、更に一歩進めて考えると「投資対象の選別より投資残高管理が更に重要」になります。
仮に安いと思われる時に投資したとしても、更に下がってしまい結果として安くない時に投資してしまっていることも多々あるはずです。よって、安いと思った時に全額を投資してしまうと結果として安い時に投資できたか否かが博打になってしまいます。安いと思った時に投資資金の一部だけを投資し、更に下がり続け大底になった時において追加投資し続けることが出来るように残高管理することが大切なのです。
これは、下がった時に追加投資する際におけるその下げ幅を大きくすればするほどリスクは小さくなり最後の大底まで投資し続けることが出来るようになりますし(投資機会が減るためリターンは少なくなります)、投資予算に対する最初の投資金額とその後の追加投資金額の割合を小さくすればするほど、やはりリスクは小さくなります(同様にリターンも小さくなります)。
私がM&Aの仲介業務を行っている時、会社の売り方である創業者の方が良く「苦労してきたのだから、高く評価して貰えるはずだ。」といった事をおっしゃられました。人間として苦労したことは当然高く評価すべきことなのでしょうが、残念ながら売買価格は全く関係がなく決められてゆきます。なぜなら、買い方は将来どの程度利益が出る(増える)か?といったことしか興味はないからです。投資をする以上、投資した後の現在の状況に応じて適切に投資資産の継続保有・売却等をし続けなくてはなりません。この際に過去のことについては全く無視して意思決定してください。
過去の事について価値があることは、その失敗や成功の経験が将来に役に立つが故、将来のためにその経験を考える必要があるといった、やはり将来対してのみ意味があるのです。(この事は投資に限らずあらゆる意思決定にあてはまりますね。)
(分散投資)
複数の投資案件に投資した場合、利回りは投資金額に応じた単純(加重)平均になります。これに対し、リスクは複数に投資(=分散投資)すればするほど低くなるのです。なぜなら、ある投資案件はプラスである時、別の投資案件はマイナスになったりして、損益を打ち消しあい、結果として損益の変動幅が小さくなるからです。
よって、理論上はリターン(収益)落とさず、分散投資によりリスクを下げることが正しいことになります。
例えば、投資対象を 国と投資の種類(株式・債券・REIT・商品等)等のマトリックスで区分して考えることが出来ます。この場合、日本の不動産に投資するといったことは、日本・不動産といった属性をもった投資案件に投資していることになります。これらの2つの切り口での区分が同一であればあるほど、損益は同様の動きをする可能性が高く分散効果が低くリスクを低くする効果は低くなります。仮に日本の不動産と日本の株式に投資した場合は、不動産と株式に固有の理由による価格の変動は互いに打ち消しあいリスクは低くなりますが、日本固有の問題が発生した時は両者ともに下落するのでこのポートフォリオでは、この日本固有のリスクは低めていない事になります。
(集中投資)
ただ、かのウォーレン・バフェットが言っている「一つの籠に全て入れて、その籠を見張れ」「分散投資は無知に対するヘッジだ。自分で何をやっているかわかっているものにとって、分散投資はほとんど意味がない。」といった発言のように、複数への投資は投資知識が十分でない状態で行われ、かつ、管理が出来ないため、分散投資せずに集中的に投資し注意深く管理することが大切であるといったこともまた真実です。
これら2つの投資方法はある意味両方とも正しいと思われます。
要は投資金額と投資体制が小さい時は集中投資を行い、その規模が一定規模を脱してきたら分散投資をすべきなのだと思われます。
1千万円の現金を保有している時に、1千万円の物件を1つ現金で不動産を買うのと、9千万円を借入して保有する現金1千万円と合計した1億円で不動産を取得した場合だと当然、利益は借金をした方が利益は多額になります。
ですので、レバレッジ(借入金の比率)を高くすればするほど、通常は利益が出るのですが、万一借入レートより不動産投資利回りが低くなれば逆に大変な損失が出てしまうこともあり得ます。短期的にはそうしたことは考えにくいのでしょうが、この20年の経済状況・不動産市況・老齢化社会・少子化等を鑑みた場合、10-30年といった中長期で考えるとどうなるか分かりません。酷くなる前に自分だけ売却してしまえばいいと思われるかしれませんが、通常自分が気付いた時には、もうマーケットの主要プレーヤーはとっくに気付いているため、自分だけ早く売却するといった期待はもつべきではないでしょう。
J-REIT等を見ると自己資本比率(=自己資本÷不動産価格)が40%程度です。よって、投資する物件以外に自分の収入無く、その他の資産が無い場合は物件価格の40%程度の頭金がリスク管理上必要と一般的には考えられているのでしょう。これを頭に入れた上、自分の投資する不動産以外の収入、当該不動産以外の資産、これら資産の分散の程度を鑑みて決めて頂きたいのですが、通常は一般的な金融機関における融資要件である10%程度の頭金は必要と考えて欲しいと思います。万一、フルローンで調達出来ても、不動産に投資することにより得られ増加したキャッシュフローは最低でも10%程度になるまで留保し続けるべきであると考えます。
■東京事務所
〒106-0032
東京都港区六本木7-3-12
六本木インターナショナルビル4F
TEL:03-5414-5055
FAX:03-5414-5056
>>お問い合せフォーム
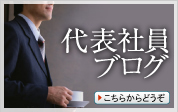
2011.10.12
山沢 滋
2011.09.29
山沢 滋
2011.04.11
山沢 滋
2011.03.14
山沢 滋
2011.01.28
山沢 滋
2011.01.11
山沢 滋
2010.10.02
山沢 滋

2013.09.18
松丸朋之
2013.08.07
新規ご契約有難うございます(神奈川県相模原市 経営コンサルティング業)
松丸朋之
2013.08.02
松丸朋之
2013.07.19
新規ご契約有難うございます(東京都練馬区 電気製品の輸入販売業)
松丸朋之
2013.06.11
松丸朋之
2013.03.05
松丸朋之
2013.02.27
松丸朋之